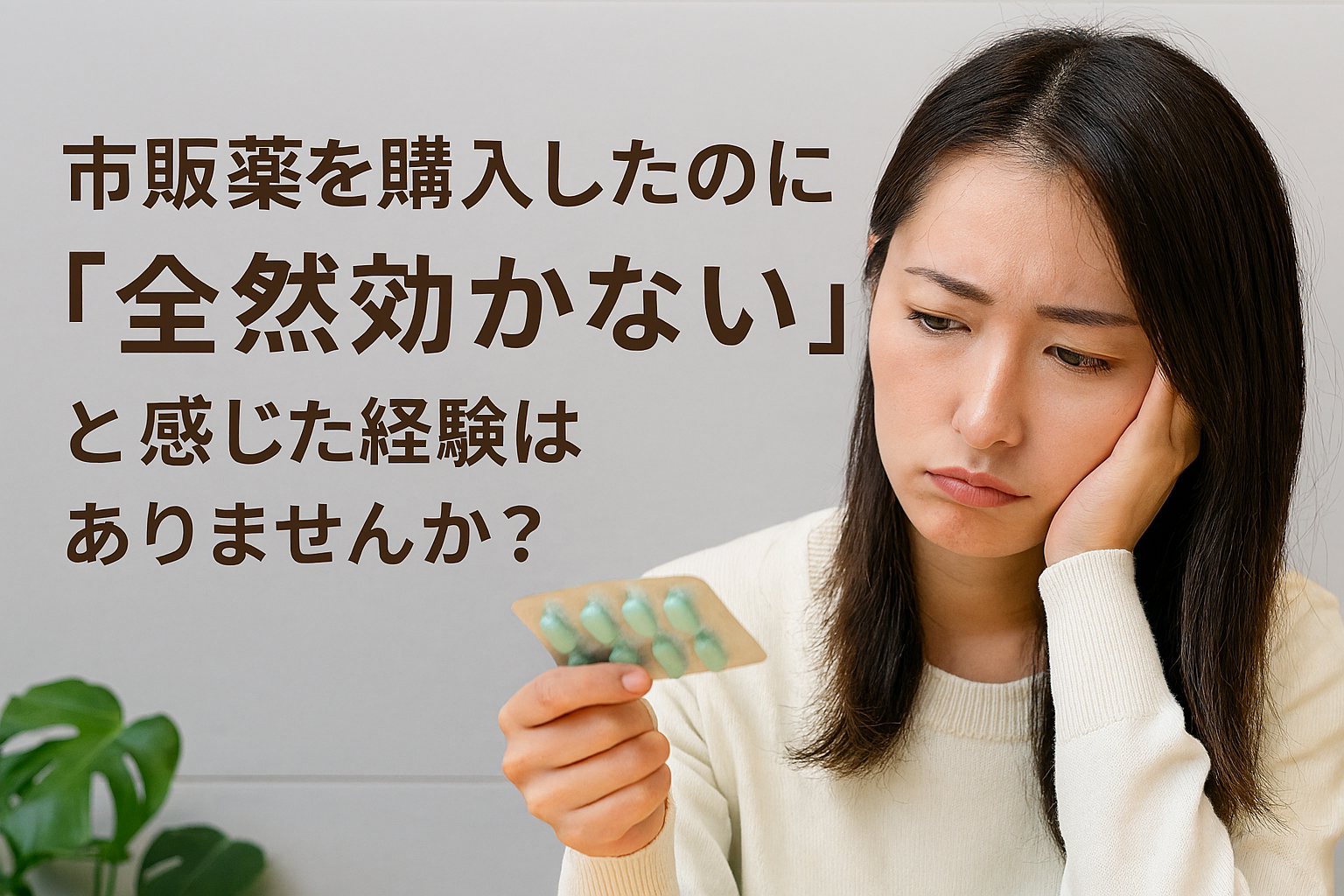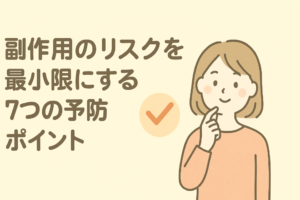3. なぜ効かない?薬剤師が明かす市販薬選びの盲点と成分表示の見方〜失敗しないための3つの秘訣〜
市販薬を購入したのに「全然効かない」と感じた経験はありませんか?実はその原因は、薬の選び方に問題があるかもしれません。薬局やドラッグストアの棚には数多くの市販薬が並んでいますが、正しく選ばなければ効果を実感できないことがあります。今回は、市販薬が効かないと感じる理由と、失敗しないための3つの秘訣をご紹介します。
■秘訣1:有効成分の種類と含有量をチェックする
市販薬の効果を左右する最も重要な要素は「有効成分」です。例えば、頭痛薬ならイブプロフェン、アセトアミノフェン、ロキソプロフェンなど、同じ症状に効くでも成分が異なります。
パッケージの裏面にある成分表示を確認し、含有量(mg数)もチェックしましょう。ロキソニンSであれば60mg、イブプロフェン配合薬なら150〜200mgが一般的な含有量です。同じ成分でも含有量が少なければ効果は弱くなります。
また、自分の体質に合わない成分もあります。過去に効果があった薬の成分をメモしておくと、市販薬の選択に役立ちます。
■秘訣2:複合成分と単一成分の違いを理解する
「総合感冒薬」や「複合鎮痛剤」といった表示がある薬は、複数の症状に対応するために様々な成分が配合されています。一方、単一成分の薬は特定の症状に特化しています。
例えば、頭痛だけなら単一成分の鎮痛剤が適していますが、熱や鼻水も伴う風邪の場合は複合薬の方が効果的です。ただし、複合薬は一つ一つの成分量が少なめに設定されていることが多いため、症状が重い場合は効果を感じにくいことがあります。
また、必要のない成分まで摂取することになるため、副作用のリスクも高まります。自分の症状に合った薬を選ぶことが大切です。
■秘訣3:剤形と吸収速度を考慮する
同じ成分でも、剤形(錠剤、カプセル、粉薬、液体など)によって体内での吸収速度が異なります。一般的に、粉薬≒液体>カプセル≒錠剤の順で吸収が早いとされています。
速やかな効果を求めるなら粉薬や液体タイプ、持続的な効果を求めるなら錠剤が適しています。また、胃が弱い方は胃への負担が少ないOD錠(口腔内崩壊錠)や、腸溶性コーティングされた製品を選ぶと良いでしょう。
さらに、薬の効果は空腹時と食後で異なることも。鎮痛剤は空腹時の方が早く効きますが、胃への刺激も強くなります。使用上の注意をしっかり読んで、適切なタイミングで服用することも重要です。
市販薬選びに失敗しないためには、これら3つのポイントを押さえるだけでなく、症状が改善しない場合は自己判断せず、医療機関を受診することも大切です。市販薬は便利ですが、万能ではありません。正しい知識で上手に付き合いましょう。